「暗いところで本を読んだりスマホを見たりすると、目が悪くなるよ」と言われた経験のある方は多いのではないでしょうか。この言葉は昔からよく聞く話ですが、実際にはそれが本当なのか、それとも単なる嘘なのか気になるところです。
本記事では、「暗いところで目が悪くなる」という話が医学的にどう捉えられているのかを、スマホ・本・テレビなどの具体的な使用シーンを交えながら解説していきます。さらに、視力に影響する本当の原因や、目が悪くならないための日常的な工夫についても分かりやすくまとめました。
照明の暗さそのものが視力低下を招くのかどうか、また暗がりでのスマホ利用がどのように目に影響するのか。そうした疑問を解消し、目の健康を守るための知識をしっかり身につけていきましょう。
- 暗いところで目が悪くなる説が本当か嘘か
- スマホや本、テレビが視力に与える影響
- 視力低下の主な原因と仕組み
- 目が悪くならないための日常習慣
暗いところで目が悪くなるは本当か嘘か?
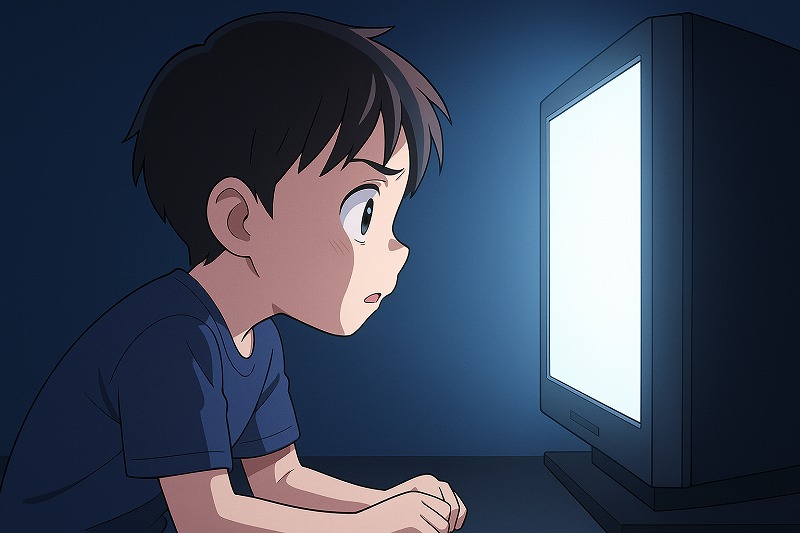
暗いところで目を使うと視力が低下する、という話は昔からよく言われています。ただし、これには医学的な根拠が明確にあるわけではありません。
暗いところで本を読むとどうなる?
暗い場所で本を読むと、目が疲れやすくなるというのは確かなことです。これは、暗がりでは文字が見えづらいため、無意識に本との距離が近くなってしまうからです。
このとき目の中では、水晶体の厚みを調節する筋肉(毛様体筋)が強く緊張しています。この筋肉が長く働き続けると、ピント調節機能がうまく働かなくなり、焦点が合いづらくなったり、視界がぼやけたりすることがあります。
さらに、視力がまだ安定していない子どもや学生が暗い環境で読書を続けると、近視が進む可能性があると考えられています。成長期は特に目の変化が起きやすい時期であるため、慎重な対応が求められます。
読書に適した明るさの目安は、教室や図書館と同程度、300ルクス以上が推奨されています。暗すぎる環境で本を読むのは避け、適度な明かりのもとで読むよう心がけることが大切です。
暗いところでスマホを見るとどうなる?
暗い場所でスマホを見ると、目に大きな負担がかかります。特に注意すべきは、スマホが自ら光を発している点です。暗がりで画面を見ると、まぶしい光が直接目に入ることになります。
この強い光は、網膜への刺激が強くなりやすく、目の奥まで届いてしまうため、目の疲労を加速させます。さらに、暗い環境では無意識にスマホを顔に近づけて見てしまう傾向があり、目との距離が20cm以下になることもあります。
このような近距離で長時間画面を見続けると、毛様体筋が過度に緊張し、眼精疲労や一時的な視力の低下を引き起こす可能性があります。さらに、画面のブルーライトの影響により、寝つきが悪くなる、睡眠の質が下がるといった影響も見逃せません。
夜にスマホを見る場合は、部屋の照明を完全には消さず、ダークモードやナイトモードを使うなどの工夫が必要です。また、画面と目の距離を30cm以上に保ち、定期的に目を休ませることで負担を軽減できます。
暗いところでテレビを見るとどうなる?
暗い部屋でテレビを見ると、目に大きな負担がかかることがあります。特に注意したいのは、部屋の明るさとテレビ画面の明るさに差がある状態です。
このとき、周囲が暗くテレビだけが明るいと、網膜に届く光の量が急激に変化しやすくなります。すると、目は明暗の差に順応しようと頻繁に調整を行うことになり、眼精疲労を引き起こしやすくなります。また、画面が見づらいと感じたとき、人は無意識に画面へ顔を近づけることがあります。この距離が縮まる行動が、結果的に目の疲れや視力への影響を招くことにもつながります。
暗い環境でテレビを観ることがすぐに病気を引き起こすわけではありませんが、長時間の視聴や、至近距離での視聴は控えたほうがよいでしょう。適度な明かりをつけて、目に負担をかけない視聴環境を整えることが重要です。特に子どもや目の疲れを感じやすい方は、意識的に注意することをおすすめします。
そもそも目が悪くなるのはなぜ?
目が悪くなる主な原因は、眼の機能が正常に働かなくなることで焦点がうまく合わなくなるためです。多くの場合、それは「屈折異常」と呼ばれる現象によるものです。
屈折異常には、近視・遠視・乱視などがあります。これらは、眼の中に入ってきた光が正確な位置に集まらず、ぼやけた像を映してしまう状態です。近視の場合、眼軸が長くなってしまい、ピントが網膜よりも手前に合ってしまいます。そのため遠くのものが見えにくくなります。
遺伝的な要因もありますが、現代では生活習慣の影響が大きいと言われています。特に近年はスマートフォンやパソコンの長時間使用、室内で過ごす時間の増加が関係しているとされ、視力への悪影響が懸念されています。
一方で、正しい姿勢や目を休める習慣を身につけることで、進行を緩やかにすることも可能です。日常の過ごし方が、目の健康を大きく左右するということを理解しておくことが大切です。
目が悪くなる原因は距離と時間だった
近視や視力低下を引き起こす要因として、目と見る対象との「距離」と、集中して見続ける「時間」は非常に重要なポイントです。これは、目の筋肉の使い方に関係しています。
人間の目は、近くのものを見るとき、ピントを合わせるために毛様体筋という筋肉を使います。この筋肉が長時間緊張し続けると、目が疲れるだけでなく、ピント調節の柔軟性が落ちてしまうことがあります。これが長期的には近視の進行につながると考えられています。
さらに、距離が近いほど毛様体筋の負担は大きくなります。例えば、スマホを20cmの距離で見るのと、テレビを2m離れて見るのでは、目への負担は大きく異なります。特に成長期の子どもは、ピント調節機能が未発達であるため、より影響を受けやすいとされます。
このように、見る距離と時間のバランスを意識することは、視力を守る上でとても重要です。30分ごとに視線を遠くに移したり、見る対象との距離を一定に保つよう心がけるだけでも、目への負担は軽減されます。
暗いところで目が悪くなるのは嘘と言えるのか?

「暗いところで目が悪くなる」という言い回しは、厳密には誤解を含んでいます。視力の低下を直接引き起こすのは、照明の明るさそのものではなく、見る距離や作業の継続時間などの要素です。
暗いところの視力低下説は医学的にどうか
暗い場所での視力低下については、現在の医学的な知見では「直接的な原因ではない」とされています。これは、多くの眼科医の見解でも一致している内容です。
視力が低下する原因の中心には、目の使い方や遺伝的な体質があります。とくに、近くを長時間見続ける行為が目の筋肉に負担をかけるとされ、それによって近視が進行する可能性があるのです。暗いところでは物が見えづらいため、顔を近づける傾向が強まり、結果的にこの「近距離作業」が発生しやすくなります。
また、暗い場所では視界のコントラストが低くなり、目が常にピントを合わせようと頑張る状態になります。この緊張が眼精疲労につながることもあるため、間接的には視力に悪影響を及ぼす環境と言えるかもしれません。
ただし、こうした影響は一時的な疲れによるものが多く、目をしっかり休ませれば回復するケースも少なくありません。そのため、暗さそのものが「視力低下の原因」とするのは、医学的には誤った理解とされています。
目が悪くならない方法はあるのか?
視力の低下を防ぐためには、日常のちょっとした習慣が大きな鍵を握ります。特別な道具や薬を使わなくても、意識次第で目への負担を減らすことが可能です。
まず大切なのは、近くを見る作業の時間を意識的に区切ることです。スマホや本を読む場合は、15~20分に1回、目線を遠くに移すだけでも毛様体筋を休ませることができます。また、照明の明るさも重要です。部屋全体が真っ暗な状態でスマホやテレビを見ないようにし、周囲との明るさの差を減らすようにすると目が疲れにくくなります。
さらに、正しい姿勢と距離も見直すポイントです。スマホや本は顔から30cm以上離すようにし、猫背にならないよう姿勢を保つことが望ましいでしょう。寝転びながら見るのは、目と画面の距離が一定にならないため避けたほうが無難です。
このような基本的な習慣の積み重ねが、長期的に見て目の健康を守る最も確実な方法と言えるでしょう。
スマホで目が悪くならない使い方とは?
スマホを使っていても、目が悪くなりにくい工夫は十分可能です。ポイントは「使い方の習慣」にあります。
まず意識したいのが、画面との距離です。目から20cm以内の距離で長時間見続けると、ピント調節を担う毛様体筋が過剰に緊張し、目が疲れやすくなります。理想的な距離は30〜40cm程度です。手元に近づけすぎないよう意識するだけでも、目への負担は軽減されます。
次に注意したいのが使用時間です。スマホはつい長時間見てしまいがちですが、15〜20分ごとに視線を画面から離し、遠くを見ることが大切です。これにより、緊張した毛様体筋を休ませることができます。
さらに、画面設定も見直す価値があります。夜間はブルーライトを抑える「ナイトモード」や「ダークモード」を活用すると、目への刺激を和らげられます。また、部屋が暗いとスマホの光が目に強く届くため、照明を完全に消さず、周囲をほどよく明るく保つことも大切です。
これらの点に気をつけることで、スマホと上手に付き合いながら目を守ることができます。
本で目が悪くならない読み方のコツ
紙の本は、スマホやタブレットに比べて目に優しいと言われていますが、読み方を間違えると視力に影響する可能性があります。
まず押さえておきたいのが、読む距離です。本は目から30〜40cmほど離して読むのが理想的です。顔を近づけすぎると、ピントを合わせる目の筋肉が緊張した状態を続けることになり、目が疲れやすくなります。
姿勢にも注意が必要です。猫背やうつ伏せの姿勢で読むと、自然と本と目の距離が近くなってしまいます。椅子に腰掛けて背筋を伸ばし、本を軽く持ち上げるようにすると、正しい距離を保ちやすくなります。
さらに、読書環境の明るさも重要です。暗い部屋では文字が見えづらくなり、目を細めたり、顔を近づけて読む傾向が強くなります。蛍光灯やデスクライトなどで、手元がしっかり明るくなるように整えるとよいでしょう。
長時間の読書を避け、30分に1回は目を休ませる習慣を取り入れることで、目の負担を減らすことができます。読書の内容に集中することは大切ですが、同時に目の健康も意識して読書時間をコントロールすることが大切です。
テレビで目が悪くならない工夫とは?
テレビを見る際に目が悪くならないようにするためには、視聴環境の整え方がとても重要です。特に「距離」「時間」「明るさ」の3点に注意を向けるだけで、目の負担を大きく減らせます。
まず、テレビとの距離を適切に取ることが基本です。画面の高さやサイズにもよりますが、目安としては画面の高さの約3倍〜5倍の距離を保つと目に優しいとされています。近くで見るほど、目のピント調整機能に負担がかかってしまいます。
次に大切なのが視聴時間の調整です。長時間続けて見ると、瞬きの回数が減り、目が乾きやすくなります。1時間に1回は画面から目を離して、遠くを見る時間をつくることが望ましいです。リモコンを活用して、姿勢を崩さずに操作できる距離をキープすることも意識してみてください。
また、部屋の明るさにも配慮が必要です。真っ暗な部屋でテレビを見ると、明るい画面との明暗差が激しくなり、目が頻繁に調整を繰り返して疲れやすくなります。間接照明やスタンドライトなどを活用して、部屋全体をほんのり明るく保つようにすると目に優しい環境になります。
こうした工夫を取り入れることで、テレビを見る時間も快適かつ健康的に過ごすことができるでしょう。
目が悪くならない生活習慣とは?
日常生活の中で視力を守るには、継続的な生活習慣の見直しが不可欠です。とくに、目を使う時間・使わない時間のバランスを意識することがカギになります。
まずは、長時間にわたって近距離作業を続けないようにすることです。スマホやパソコンを使うとき、本を読むときなど、15〜20分ごとに意識的に遠くを見る時間を設けると、目の緊張がやわらぎます。遠くを見ることで、ピントを合わせる筋肉がリラックスできるからです。
また、睡眠も目の健康に密接に関係しています。睡眠不足は目の回復力を下げ、眼精疲労の原因になることがあります。質の良い睡眠をしっかり確保することで、翌日の目の疲れも感じにくくなります。
食事の内容も無視できません。緑黄色野菜に含まれるルテインや、ブルーベリーに含まれるアントシアニンなどは、目の疲労回復に役立つとされている栄養素です。意識的に取り入れることで、日常的な目のケアにつながります。
さらに、屋外で過ごす時間も重要です。外の自然光を浴びることで、目の緊張がほぐれ、近視の進行を抑える効果があると考えられています。日中に散歩や軽い運動を取り入れるだけでも、目にとって良い影響があります。
このような生活習慣を日常に取り入れることで、無理なく視力低下のリスクを減らしていくことができます。
暗いところで目が悪くなるは嘘?まとめ
「暗いところで目が悪くなる」という言い方は、昔からよく知られた常識のように扱われてきましたが、医学的に見ると必ずしも正しいとは言えません。照明の暗さ自体が視力低下を直接引き起こすという明確な根拠はなく、むしろ重要なのは「見る距離」や「時間の長さ」にあります。
暗い場所では物が見えにくくなるため、自然と目との距離が近づき、結果として毛様体筋に負担がかかりやすくなるのです。これはスマホ・本・テレビすべてに共通する問題です。つまり、「暗いところで目が悪くなる」は完全な嘘ではありませんが、誤解を含んだ表現だと言えます。
視力を守るには、適度な明るさ・距離・作業時間の管理、そして生活習慣全体の見直しが必要です。正しい知識と意識的な対策によって、目への負担を大きく減らすことができます。

