日常生活の中で、「思い通りにならないとキレる人」に悩まされることはありませんか?家族や職場の人間関係において、些細なことで怒りを爆発させる人がいると、周囲の人は困惑してしまいます。このような行動は単なる性格の問題ではなく、障害が関係している可能性もあります。
怒りっぽさの原因としては、間欠性爆発性障害や発達障害、ストレスやホルモンバランスの乱れなど、さまざまな要素が考えられます。特に、家では感情を抑えられず家族にだけ強く当たってしまうケースも少なくありません。
この記事では、思い通りにならないとキレる人の特徴や考えられる障害の種類、そして具体的な対処法について詳しく解説します。もし身近な人が怒りをコントロールできずに悩んでいる場合、適切な対応を知ることで、より良い関係を築くヒントが得られるかもしれません。
- 思い通りにならないとキレる人の原因と考えられる障害の種類
- 怒りやすい人に見られる特徴と家族にだけキレるケースの理由
- 怒りをコントロールするための具体的な対処法
- 病気の可能性がある場合の適切な受診先と治療方法
思い通りにならないとキレる人は障害なのか?

●思い通りにならないとキレる人の主な原因
●家族にだけキレる病気とは?大人に見られる特徴
●怒る病気にはどんな種類があるのか?
●発達障害と怒りっぽさの関係
大人がすぐ怒るのは病気の可能性もある
大人になっても感情のコントロールが難しく、些細なことで怒ってしまう場合、それが単なる性格ではなく、何らかの病気が関係している可能性があります。
このような状態が続く場合、間欠性爆発性障害や発達障害(ADHD・ASD)、うつ病・双極性障害などが関係していることがあります。例えば、間欠性爆発性障害の人は衝動的に怒りを爆発させた後に後悔することが多く、発達障害の人は環境の変化や自分の考えと違うことが起こると強いストレスを感じ、怒りを抑えにくい傾向があります。
また、ホルモンバランスの乱れやストレスによる自律神経の乱れが原因となるケースも少なくありません。更年期障害や月経前症候群(PMS)では、イライラや怒りっぽさが強くなることがありますし、長期的なストレスが溜まることで感情のコントロールが難しくなることもあります。
こうした病気が疑われる場合、怒りの原因を突き止めるために心療内科や精神科で相談することが重要です。特に、怒りが日常生活や対人関係に支障をきたしている場合は、専門的な治療やサポートを受けることで改善が期待できます。
思い通りにならないとキレる人の主な原因
思い通りにならないとすぐに怒ってしまう背景には、心理的要因・脳の働き・環境要因など、さまざまな理由が考えられます。
まず、心理的要因としては、自己中心的な考え方やストレス耐性の低さが影響していることがあります。自分の価値観やルールに強くこだわる人は、想定外の出来事に直面すると、過剰にイライラしてしまうことが多いです。また、過去のトラウマや、幼少期に怒りのコントロールを学ぶ機会が少なかった場合も、衝動的に怒る傾向が強くなります。
次に、脳の働きも関係しています。発達障害の一つであるADHD(注意欠如・多動症)の人は、衝動性が高いため、感情を抑えずにすぐに怒ってしまうことがあります。また、セロトニンという神経伝達物質が不足すると、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなることが知られています。
さらに、環境要因も見逃せません。例えば、家庭や職場でのストレスが溜まっていると、些細なことで爆発してしまうことがあります。特に、家族にだけキレるというケースでは、外で抑えていたストレスが家で解放されてしまうことが原因となることが多いです。
このように、思い通りにならないとキレる原因は単純なものではなく、複数の要因が絡み合っています。対策としては、自分の怒りの原因を知ること、ストレス管理を意識すること、そして必要であれば専門医に相談することが大切です。
家族にだけキレる病気とは?大人に見られる特徴

家では些細なことで怒りを爆発させるのに、職場や友人の前では感情を抑えられる。このようなケースでは、家族にだけキレる病気の可能性が考えられます。
特に、大人に見られる特徴として「間欠性爆発性障害」や「発達障害(ADHD・ASD)」が挙げられます。間欠性爆発性障害の人は、衝動的に怒りを爆発させるものの、短時間で収まり、後悔や自己嫌悪に陥ることが多いです。一方、発達障害の人は環境の変化に敏感であり、家ではリラックスできる分、自分の感情を抑えにくくなることがあります。
また、「うつ病」や「双極性障害」も影響を与えることがあります。うつ病の人はストレスや疲労が蓄積すると、身近な人に対して攻撃的になりやすい傾向があります。双極性障害の場合、躁状態のときは気分が高揚し、イライラしやすくなるため、家族に怒りをぶつけてしまうことがあります。
さらに、「月経前症候群(PMS)」や「更年期障害」も要因の一つです。ホルモンバランスが乱れることで、感情の起伏が激しくなり、家族との些細なやり取りで怒りが爆発することがあります。
このような状態が続くと、家族関係が悪化し、孤立感やストレスが増す可能性があります。もし、自分でも怒りをコントロールできないと感じる場合は、一度専門医に相談することを検討しましょう。
怒る病気にはどんな種類があるのか?
怒りっぽさが目立つ場合、それが単なる性格の問題ではなく、精神的な疾患や神経系の異常が関係していることがあります。以下では、怒りと関係が深い主な病気を紹介します。
1. 間欠性爆発性障害(IED:Intermittent Explosive Disorder)
この病気は、小さなことで爆発的に怒りを爆発させるのが特徴です。怒りの持続時間は短く、すぐに収まることが多いですが、怒っている間は周囲を威嚇したり、物に当たったりすることもあります。
特徴的な症状
- 怒りが突然爆発し、手がつけられなくなる
- 口論や暴力的な行動に発展することがある
- 怒った後に後悔するが、繰り返してしまう
原因と治療
脳の前頭葉の機能異常や、神経伝達物質(特にセロトニン)の不足が関係していると考えられています。治療としては、認知行動療法(CBT)による衝動のコントロールや、必要に応じて抗うつ薬や気分安定薬が処方されることがあります。
2. 双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は、気分の波が激しく、怒りっぽくなる時期(躁状態)と、気分が落ち込む時期(うつ状態)を繰り返す病気です。特に躁状態では、感情が高ぶりやすく、些細なことでイライラし、怒りが爆発することがあります。
特徴的な症状
- 気分が異常に高揚し、活動的になる(躁状態)
- 些細なことでも怒りやすくなる
- 反対に、気分が落ち込む時期(うつ状態)もある
原因と治療
脳の神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)のバランスの乱れが原因とされています。治療には、気分安定薬(リチウムやバルプロ酸など)が用いられ、医師の指導のもとで適切な管理が必要です。
3. 反応性アタッチメント障害(RAD:Reactive Attachment Disorder)
幼少期に親との適切な愛着関係が築けなかった場合、大人になってから感情のコントロールが難しくなり、強い怒りを感じることがある病気です。特に、人間関係のトラブルが多く、対人ストレスで爆発的な怒りを表すことがあります。
特徴的な症状
- 人と親密な関係を築くのが苦手
- 怒りの感情が極端に強くなる
- 些細なことで攻撃的な態度を取る
原因と治療
幼少期のトラウマやネグレクト(育児放棄)が原因になることが多いです。治療には、カウンセリングや心理療法が用いられ、徐々に怒りの原因を理解し、コントロールする練習を行います。
4. 発達障害(ADHD・ASD)
発達障害のある人は、感情のコントロールが苦手で、怒りやすい傾向があります。特に、ADHD(注意欠如・多動症)の人は衝動的に怒りを爆発させやすく、ASD(自閉スペクトラム症)の人は自分のこだわりが崩れると強くイライラすることがあります。
特徴的な症状
- ADHD:衝動的に怒りを表し、後で後悔する
- ASD:予定やルールが乱れると強い怒りを感じる
- 怒る理由が周囲には理解しづらいことがある
原因と治療
脳の発達の違いが影響しているため、行動療法や環境調整が重要です。また、必要に応じてストラテラやコンサータなどのADHD治療薬が処方されることもあります。
5. うつ病・適応障害
うつ病や適応障害と聞くと「気分が落ち込む病気」というイメージがありますが、実はイライラや怒りっぽさが目立つケースもあるのです。特に、男性のうつ病では、怒りとして症状が現れることが多いとされています。
特徴的な症状
- 些細なことで怒りを感じる
- 周囲に対して攻撃的になることがある
- 疲れやすく、意欲が低下する
原因と治療
ストレスやホルモンバランスの変化が影響しています。治療には、抗うつ薬(SSRI・SNRIなど)が用いられ、心理療法と組み合わせることで回復を目指します。
発達障害と怒りっぽさの関係
発達障害の中でも、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)は怒りっぽさと関連が深いとされています。
ADHDの人は、もともと衝動性が強いため、思ったことをすぐに言葉や行動に移してしまう傾向があります。例えば、ちょっとしたことでイライラしやすく、衝動的に怒鳴ったり物に当たったりすることがあります。また、集中力が続かないことや、計画通りに物事が進まないことがストレスとなり、怒りにつながるケースも少なくありません。
一方、ASDの人は、環境の変化や予測できない出来事に対して強いストレスを感じることが特徴です。例えば、ルールが守られなかったり、自分の思い通りにいかない状況に直面したりすると、強い怒りを感じることがあります。また、感覚過敏がある場合、特定の音や光、匂いなどに対して強い不快感を覚え、それが怒りにつながることもあります。
また、発達障害の人は、怒りを適切に表現する方法を学ぶ機会が少なかったり、自分の感情を言葉で伝えることが苦手だったりすることが多いです。そのため、フラストレーションがたまりやすく、結果として怒りっぽくなることがあります。
こうした特性を持つ人は、怒りを抑えようとするよりも、怒りの原因を知り、事前に回避する方法を考えることが大切です。また、環境を整えたり、リラックスできる時間を意識的に作ったりすることで、怒りの爆発を減らすことができるかもしれません。もし怒りが日常生活に影響を及ぼしている場合は、専門医に相談し、自分に合った対策を取ることをおすすめします。
思い通りにならないとキレる人の障害と対処法

●家族にだけキレる大人が気をつけるべきこと
●怒る病気が疑われる場合の受診先
●発達障害による怒りの対策とサポート方法
●生活習慣を改善して怒りを抑える方法
●怒りを抑えられないときの心療内科・精神科の活用
怒りをコントロールするための対処法
怒りを抑えようと意識しても、衝動的に爆発してしまうことがあります。これは、単に「我慢が足りない」わけではなく、怒りのメカニズムを理解し、適切な対処を行うことが重要です。
まず、「アンガーマネジメント」を実践することで、怒りをコントロールしやすくなります。例えば、怒りを感じたときに6秒間深呼吸することで、衝動的な行動を抑えられる可能性があります。また、怒りを数値化し、「今の怒りは10段階中どのレベルか?」と客観的に考える習慣をつけるのも有効です。
次に、「怒りの引き金(トリガー)」を知ることも重要です。自分がどんな状況で怒りを感じやすいのかを振り返り、事前に回避できる工夫をすることで、怒る頻度を減らせます。例えば、「仕事の疲れが溜まるとイライラしやすい」と気づけば、意識的に休息を取ることが対策になります。
さらに、「感情の言語化」も役立ちます。怒りを感じたとき、「なぜ自分は今怒っているのか?」を言葉にして整理すると、怒りの本質が見えてきます。特に、紙に書き出すことで、冷静に状況を振り返ることができるでしょう。
怒りを完全になくすことは難しいですが、適切な対処法を身につけることで、怒りの爆発を減らし、穏やかに過ごせる時間を増やすことができます。
家族にだけキレる大人が気をつけるべきこと
家では怒りっぽくなってしまうのに、職場や友人の前では冷静でいられる。このような場合、怒りの矛先が家族に向かいやすくなっている可能性があります。特に、「甘え」と「ストレスの蓄積」が大きな要因になっていることが多いです。
まず、家族を「怒っても許してくれる存在」と考えないことが大切です。家族にだけ怒りをぶつける癖がつくと、関係が悪化し、最終的に家族の協力を得られなくなる可能性があります。もし、普段から怒りを爆発させてしまうなら、一度「自分がされたらどう思うか?」を考える習慣をつけましょう。
次に、「自分のストレスを自覚すること」も重要です。仕事や対人関係のストレスが溜まると、無意識のうちに最も身近な家族に八つ当たりしてしまうことがあります。これを防ぐためには、こまめにストレスを発散することが必要です。運動や趣味の時間を持つ、睡眠をしっかり取るなど、ストレス管理を意識しましょう。
また、「怒りを表現する方法を見直す」こともポイントです。怒りを感じたときに、すぐに声を荒げるのではなく、「今、自分は怒っている」と冷静に伝える習慣をつけるだけで、家族との関係が改善されることがあります。「○○が嫌だった」と具体的に伝えることで、感情的な言い合いを避けることができます。
家族との関係を大切にするためにも、「なぜ家族にだけキレるのか?」を振り返り、怒りをコントロールする方法を意識的に実践することが重要です。
怒る病気が疑われる場合の受診先
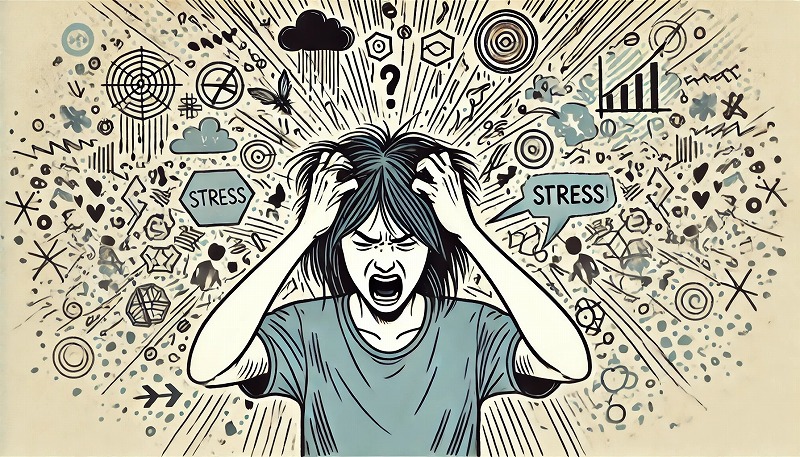
もし、自分自身や身近な人が「怒りを抑えられない」「キレやすくて困っている」と感じた場合、専門の医療機関に相談することが大切です。怒りの原因には精神的な疾患や発達障害が関係している可能性があるため、適切な診断と治療を受けることで改善が期待できます。
まず、「精神科」や「心療内科」が一般的な受診先になります。間欠性爆発性障害やうつ病、双極性障害などが疑われる場合、専門医による診断を受けることで、薬物療法やカウンセリングなどの治療が受けられます。
また、発達障害の可能性がある場合は、「発達障害専門のクリニック」や「精神科」での診察が推奨されます。特にADHDやASDの特徴に当てはまる場合、専門医による診断を受けることで、自分に合った対策を知ることができます。
もし、すぐに医療機関を受診することに抵抗がある場合は、自治体の「精神保健福祉センター」や「心の健康相談窓口」を利用するのも一つの方法です。専門医がいる施設ではないものの、どの診療科を受診すべきかのアドバイスを受けることができます。
怒りのコントロールに悩んでいる場合、「自分の性格だから仕方ない」と思い込まずに、専門機関に相談することで、より適切な方法で改善を目指すことができます。
発達障害による怒りの対策とサポート方法
発達障害の特性として、感情のコントロールが難しいことがあります。特に、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)の人は、環境の変化や予期しない出来事に対して強いストレスを感じやすく、その結果として怒りを爆発させてしまうことがあります。これを軽減するためには、本人が取り組める対策と周囲のサポートの両方が重要です。
まず、怒りを感じたときに自分を落ち着かせる方法を身につけることが大切です。例えば、「怒ったらその場を離れる」「深呼吸をする」「頭の中で10秒数える」といったシンプルな方法でも、怒りの衝動を抑えるのに効果があります。
また、ストレスを事前に減らすために、自分にとって快適な環境を整えるのも有効です。音や光に敏感な人なら、騒がしい場所を避けたり、静かな時間を確保したりすることで、ストレスを減らせるでしょう。
次に、周囲のサポートも重要です。発達障害のある人が怒りを爆発させる場面では、「なぜ怒っているのか」「どんな支援が必要か」を冷静に理解し、適切に対応することが求められます。
例えば、「指示を具体的に伝える」「予測できるスケジュールを立てる」などの配慮をすることで、不安やストレスを軽減できる可能性があります。
また、発達障害の特性を理解し、怒りをコントロールする方法を学ぶためには、専門のカウンセリングや発達障害支援センターを活用するのも一つの手です。怒りをコントロールする訓練を受けることで、徐々に適切な感情のコントロールができるようになるでしょう。
生活習慣を改善して怒りを抑える方法

怒りやすい人の中には、生活習慣の乱れが影響しているケースも少なくありません。特に、睡眠不足や食生活の偏りは、脳の働きに影響を与え、感情のコントロールを難しくする要因になり得ます。これらを改善することで、怒りの爆発を減らせる可能性があります。
まず、十分な睡眠を確保することが重要です。睡眠不足になると、脳の前頭葉の働きが低下し、感情のコントロールが難しくなります。特に、大人でも最低6~7時間の質の良い睡眠をとることが推奨されます。寝る前にスマホやパソコンの使用を控え、規則正しい生活リズムを作ることで、より安定した精神状態を保つことができます。
次に、食生活の見直しも大切です。血糖値が急激に変動すると、イライラしやすくなることがあります。そのため、白米やパンなどの糖質中心の食事ではなく、タンパク質やビタミンB群を含む食品(卵、ナッツ、魚、野菜など)をバランスよく摂取することが推奨されます。また、カフェインやアルコールの過剰摂取も、興奮状態を引き起こしやすいため、控えめにすることが望ましいでしょう。
さらに、適度な運動を取り入れることも有効です。運動をすることでストレスホルモンが減少し、リラックスしやすくなります。特に、ウォーキングやヨガ、軽いストレッチは、怒りを感じにくい心の状態を作るのに役立ちます。
このように、生活習慣を整えることで、怒りっぽさを軽減することが可能です。毎日の習慣を少しずつ改善し、穏やかな心を保ちやすい環境を作ることを意識してみましょう。
怒りを抑えられないときの心療内科・精神科の活用
「些細なことで怒りが爆発する」「怒りを抑えようと思っても無理」などの状態が続く場合、単なる気分の問題ではなく、精神的な疾患や脳の機能に関係している可能性があります。そのようなときは、心療内科や精神科を受診することが有効です。
まず、怒りのコントロールができない場合、「間欠性爆発性障害」や「うつ病」「双極性障害」といった精神的な疾患が関与していることがあります。これらの病気は、本人の意志ではコントロールが難しいため、専門医の診断を受け、適切な治療を行うことが重要です。
また、発達障害が関係している場合もあります。特に、ADHDやASDの人は、衝動的に怒りを爆発させやすい傾向があります。こうした場合も、専門医に相談することで、自分に合った対策や治療を知ることができます。
心療内科や精神科では、薬物療法とカウンセリングの両方を組み合わせた治療が一般的です。例えば、怒りの衝動を抑えるために、抗うつ薬や気分安定薬が処方されることがあります。また、認知行動療法などのカウンセリングを受けることで、怒りの根本的な原因を理解し、適切な対処法を学ぶことができます。
医療機関を受診することに抵抗がある場合、自治体の相談窓口や精神保健福祉センターを活用するのも一つの方法です。医療機関に行く前の相談として利用でき、適切な受診先を紹介してもらえることもあります。
怒りをコントロールできない状態が続くと、人間関係や仕事にも影響を及ぼす可能性があります。「自分ではどうにもできない」と感じたときは、一人で悩まずに、専門医に相談してみることが大切です。
総評:思い通りにならないとキレる人は障害が関係しているのか?
思い通りにならないとキレる人の背景には、心理的要因・脳の機能・環境要因が複雑に絡んでいることがあります。特に、間欠性爆発性障害や発達障害(ADHD・ASD)、うつ病・双極性障害などが関係している可能性があります。
加えて、ホルモンバランスの乱れやストレスも影響を与えることがあり、生活習慣の見直しや専門医への相談が重要になります。
家族にだけキレるケースでは、甘えやストレスの発散が影響していることも考えられます。
怒りをコントロールするためには、ストレス管理やアンガーマネジメントが有効ですが、症状が深刻な場合は心療内科や精神科での診断・治療を検討することが大切です。

